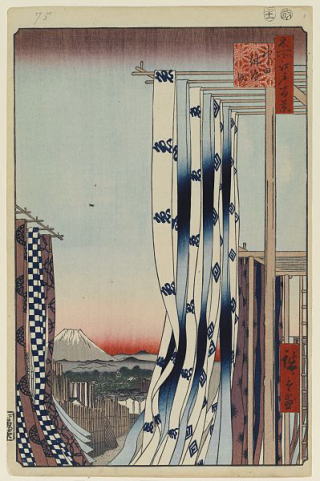最上級の遊女であった太夫は、遊郭という場所柄、きらびやかな生活や、男女の仲にまつわる逸話を残すものがほとんどです。
数少ない例外となるのが「薄雲太夫(うすくもたゆう)」です。
猫を愛した太夫と、招き猫のモデルとなった愛猫の話をご紹介します。
薄雲太夫とは
太夫の名は襲名制で、薄雲太夫の称号を受けた女性は、歴史の中に3名ほど存在します。
しかし、元禄年間(1688~1704年)に薄雲太夫の称号を継いだ女性以外は、詳しいことは分かっていません。
そのため、今回触れる薄雲太夫も、何代目にあたるのかも定かではありません。
ただし、初代が万治(1658~1661年)の人物だったという説があるため、2代目ないし3代目であると考えられます。
薄雲の名は、平安時代の長編小説である『源氏物語』の第19巻の巻名から来ているとされています。
藤壺の死などが描かれている巻なので、どこか儚い印象がありますね。
薄雲太夫は、1700年に350両で身請けされ、吉原を後にしますが、その後人生は誰も知ることがありません。
薄雲太夫と愛猫「玉」
薄雲太夫の猫好きは、吉原においても有名で、寝ても覚めても、「玉」という名の愛猫を側に置いていたと言います。
猫といえば「たま」というお約束は、この時代でも有効だったようですね。
しかも、三毛猫だったというのですから、元祖日本猫という感じがします。
玉を猫かわいがりしていた薄雲太夫は、緋縮緬(ひぢりめん)の首輪に純金の鈴を与え、馴染みの客よりも大切にしていたと言われています。
お客の中には、玉に嫉妬して「猫になりたい!」と切望する者も多かったのだとか。
しかし、あまりにも太夫が溺愛するため、「太夫は化け猫に取り憑かれてしまったのでは」という噂が、遊郭内に流れ始めました。
太夫の身を案じた見世の主人は、玉を手放すように説得しますが、太夫は納得しませんでした。
そんな中、玉も玉で、太夫の側を離れようとしません。
どこに行くにも、太夫の後ろをついてまわり、化け猫疑惑をさらに高めていきました。
そして、とうとう厠の中にまで一緒に入ろうとする玉の首を、見世の者が切り落としてしまったのです。
ここで話が終わるかと思えば、そうでもなく、切り落とされた玉の首が驚くべき動きをしました。
厠の中まで飛んで行き、隠れていた蛇の頭に噛み付いて、事切れたのです。
玉は、蛇に付きまとわれる薄雲太夫の身を案じて、守ろうとしていたのです。
招き猫となった「玉」
誰よりも愛する玉を亡くした薄雲太夫は、失意の底にいました。
西方寺という寺に、玉のための猫塚を立てても、心癒やされません。
玉を思っては、涙ぐむ太夫。
憐れに思った一人の客が、長崎から一尺(約30cm)もの伽羅の銘木を取り寄せ、玉の姿を刻みました。
その際に参考にしたのが、「狐が顔を洗うために、左手で耳を触れば、お客が来る」という意味の中国の故事だったと言われています。
狐の姿を、玉に置き換えて、薄雲太夫に贈ったのです。
縁起物を何よりも大切にした、遊郭ならではの贈り物ですね。
玉の彫り物は「招き猫」のモデルとなり、薄雲太夫の死後、西方寺に収められたと言われています。
しかし、残念なことに、江戸末期に起きた家事が原因で、寺は全焼。
玉の彫り物も、このときに失われてしまいました。
玉をモデルにした招き猫が、現代にまで伝わっている理由は、西方寺の玉の彫り物を真似た縁起物が売り出されたためです。
木彫りではなく、今戸焼という焼き物で、右手を上げた招き猫を作ったところ、大流行したと言われています。

招き猫
薄雲太夫 まとめ
歌舞に秀でていたとされている薄雲太夫ですが、玉との逸話のおかげで、招き猫エピソードの方が有名になっていました。
子どもとペットに勝てないのは、世の常なのかもしれません。

海外に在住しながらライティングしています。